2024.2.29|ブログ
令和5年度介護現場における生産性向上推進フォーラム
2024.2.27
「令和5年度介護現場における生産性向上推進フォーラム」
13:30〜17:30 WEB
主催:厚生労働省
後援:厚生労働省老健局高齢者支援課
後援:介護業務効率化・生産性向上推進室
Ministry of Health, Labour and Welfare in Japan
≪介護現場の生産性向上等を通じた働きやすい職場環境づくり≫
現在でも、介護保険制度を取り巻く状況は厳しい。
<65歳以上の高齢者数>
2025年予想 3677万人
2042年予想 3935万人(ピーク予想)
2055年予想 3704万人
<75歳以上の高齢者数>
2025年予想 2180万人 (17.8%)
2055年予想 2446万人 (25.1%)
※%は全人口に占める割合
<介護職員の必要数>
2025年迄には243万人は必要
2040年迄には280万人は必要
※国においては
①介護職員の処遇改善
②多様な人材の確保・育成
③離職防止・定着促進・生産性向上
④介護職の魅力向上
⑤外国人材の受け入れ等検討
このことから、介護現場における生産性向上の取り組みを考え、ま
일본의 고령자가 늘어나면서 간병 문제는 심각한 상황이다.대책 회의에 참가했다.
随着日本高龄者的增加,护理问题非常严重。参加了对策会议。
With the number of elderly people in Japan increasing, the nursing care problem is a serious.I participated in the countermeasure meeting.

2024.2.22|ブログ
エベレンゾWEBシンポジウム
「エベレンゾWEBシンポジウム」
17:00~17:45 WEB勉強会
主催:アステラス製薬株式会社
≪令和6年度診療報酬の最新情報≫
<透析医療におけるHIF-PH阻害薬の使い方>
患者が増加すると医療費負担が大きくなる
診療報酬が減額した分を加算で補う
診療報酬減額分、適切な医療サービスが維持できるのか?
透析の材料費なども、最近軒並み上がってきている
電気水道代も高騰。働き方改革でスタッフのコスト増
廃業する透析施設も・・・これ以上の診療報酬減額は透析医療を破
キーワード:腎代替療法専門指導士・・・全国で約2000名
⇒透析患者さんの治療選択に関わることにより新たな加算を想定・
腎代替療法専門指導士がいれば加算を取得できそうだが・・・いな
・・・増えることを期待しております
透析医療だけではないと思うが、
適切な医療を維持することも財政的に難しいところまで来ているよ
2024년도의 진료 보수 개정의 최신 정보를 들었습니다.
听了2024年度诊疗报酬修订的最新信息。
I listened to the latest information on the revision of medical fees for 2024.
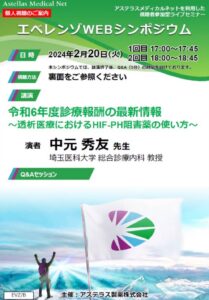
2024.2.21|ブログ
おやつセミナー
2024.2.20
「おやつセミナー」
コルスバ(静注透析搔痒症改善剤)
KORSUVA® IV Injection Syringe for Dialysis
ジフェリケファリン酢酸塩(Difelikefalin Acetate)
主催:キッセイ薬品工業株式会社
抗搔痒作用を持つκオピオイド受容体作動薬で、透析医療現場での
搔痒症は、痒みの原因となる明らかな皮膚病変がないにも関わらず
痒みは長期にわたり継続し、強い精神的苦痛に繋がることから、著
コルスバ(KORSUVA)は、選択的なκオピオイド受容体(K
当院でも、掻痒症の透析患者さんに使用しており、〝痒みが治まっ
Difelikefalin Acetate가 투석환자의 가려움 증상을 완화시킬 것으로 기대한다.
期待Difelikefalin Acetate能缓解透析患者的瘙痒症状。
It is hoped that Diffelikefalin Acetate will relieve itching symptoms in dialysis patients.


Archives
- 2024年4月 (11)
- 2024年3月 (12)
- 2024年2月 (13)
- 2024年1月 (5)
- 2023年12月 (19)
- 2023年11月 (14)
- 2023年10月 (10)
- 2023年9月 (18)
- 2023年8月 (13)
- 2023年7月 (10)
- 2023年6月 (19)
- 2023年5月 (16)
- 2023年4月 (23)
- 2023年3月 (23)
- 2023年2月 (12)
- 2023年1月 (9)
- 2022年12月 (21)
- 2022年11月 (12)
- 2022年10月 (12)
- 2022年9月 (11)
- 2022年8月 (11)
- 2022年7月 (8)
- 2022年6月 (14)
- 2022年5月 (12)
- 2022年4月 (8)
- 2022年3月 (8)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (10)
- 2021年12月 (15)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (8)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (10)
- 2021年6月 (8)
- 2021年5月 (11)
- 2021年4月 (8)
- 2021年3月 (14)
- 2021年2月 (5)
- 2021年1月 (9)
- 2020年12月 (9)
- 2020年11月 (13)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (16)
- 2020年8月 (5)
- 2020年7月 (12)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (9)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (14)
- 2019年12月 (13)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (20)
- 2019年8月 (10)
- 2019年7月 (17)
- 2019年6月 (15)
- 2019年5月 (10)
- 2019年4月 (16)
- 2019年3月 (12)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (8)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (19)
- 2018年10月 (17)
- 2018年9月 (12)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (14)
- 2018年6月 (10)
- 2018年5月 (8)
- 2018年4月 (15)
- 2018年3月 (20)
- 2018年2月 (10)
- 2018年1月 (9)
- 2017年12月 (7)
- 2017年11月 (13)
- 2017年10月 (8)
- 2017年9月 (22)
- 2017年8月 (9)
- 2017年7月 (15)
- 2017年6月 (18)
- 2017年5月 (5)
- 2017年4月 (11)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (8)
- 2016年12月 (2)
- 2016年11月 (3)
- 2016年7月 (2)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2014年11月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年5月 (2)
- 2014年4月 (1)